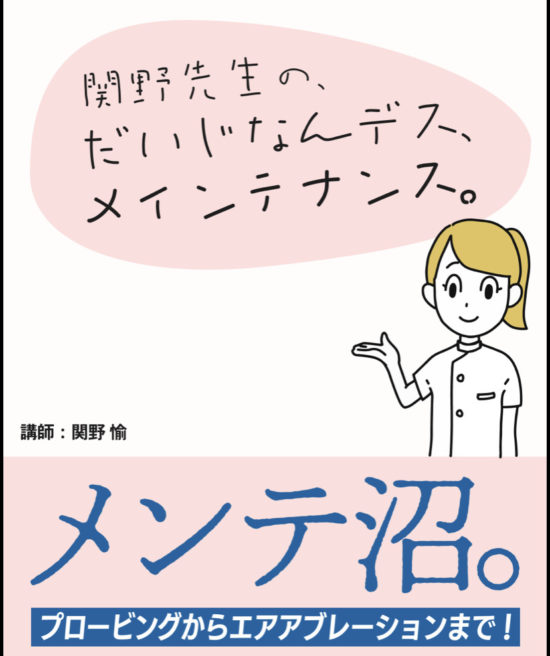
こんにちは!いつもお世話になっています、歯科衛生士の並木です。
先日、全2回にわたって
『だいじなんデス、メインテナンス、ようこそメンテ 沼の世界
沼の世界 へ』
へ』
と題した関野愉先生のセミナーに参加しました。
このセミナーでは、正確な歯周病の検査についての手技のポイントや、
正確な知識、歯面清掃法を効率よく確実に行うための方法を教えて頂きました。
正確な知識、歯面清掃法を効率よく確実に行うための方法を教えて頂きました。
1.歯周病の検査の3つの順番
歯周病の検査の順番は以下のとおりです
・プロービング検査
・歯周ポケットの深さ
・歯周ポケットの深さ
・レントゲン検査
・歯を支える骨の状態
・プラークの付着検査
・清掃状況
このような検査を主に行います。
1-1.プロービング検査と担当衛生士制が歯周病治療のカギ!
医療というのは日々進歩していますが、
①のプロービングという歯周ポケット検査だけは、何年経ってもこれにとって変わる検査法がありません

CBCT【(コーンビームCT)歯科専用CT】を撮れば、骨吸収状態が精密に把握できますが、
CBCT撮影は3ヶ月おきに行うメインテナンスでは毎回ごとに保険適用範囲内では撮影できない事(つまり自費診療になること)と、X線では把握できない炎症状態は、プロービング検査でしか 確認できません
確認できません
CBCT撮影は3ヶ月おきに行うメインテナンスでは毎回ごとに保険適用範囲内では撮影できない事(つまり自費診療になること)と、X線では把握できない炎症状態は、プロービング検査でしか
歯周組織状態を知る重要な検査になりますので、毎回数値が違うことを防ぐ為には
患者様には、同じ衛生士が担当させて頂く事で誤差をなくし、X線と照らし合わせながら同じ圧力と同じ位置を意識することでより
精密な検査ができることを学びました。
精密な検査ができることを学びました。
2.検査結果をどう読み解くか、答えは「医療面接」!
「なぜ、どうして?」
と現在、口の中で何が起こっているのかを読み解く原因となる鍵は、
患者様に対して医療面接が重要になってきます。
患者様に対して医療面接が重要になってきます。
いつから症状があるのか、生活環境、全身疾患、喫煙状況、服薬状況等を把握するのは
口腔内の検査だけではわかりません。
初診時は勿論、普段の何気ない会話からも読み取り、
検査結果の根拠を知るスキルを身につけることで歯周治療の見え方が変わる事を学びました。
検査結果の根拠を知るスキルを身につけることで歯周治療の見え方が変わる事を学びました。
3.メインテナンスが歯周病予防に大切!
歯周病は再発しやすい病気 なので治療終了した後のメインテナンスが大切になります。
なので治療終了した後のメインテナンスが大切になります。
治療により安定した口腔内を維持するために、定期的なメインテナンスを受け、
リスクの残っている部位は、それに合わせた治療や清掃が必要になります
衛生士は、患者さんの一番近くにいる存在から、
口腔内の変化にいち早く気付き、
アンテナを張る必要があることを学びました。
口腔内の変化にいち早く気付き、
アンテナを張る必要があることを学びました。
4.まとめ
関野先生のセミナーはとても分かり易く、明日から役立つ内容ばかりでした。
質疑応答では、参加者からの質問も多数あり、普段から疑問に感じていた事が次々に解決となり、とても貴重なセミナーとなりました。
歯周病について勉強を始めた頃、先生の本を読み、こちらにも感想を書かせて頂きました。先生の本に書かれている内容は、すべてに根拠があり、信頼のおける一冊として私のバイブル となり、今も迷った時に読み返しています。
となり、今も迷った時に読み返しています。
セミナーに参加した事で、自分の手技や知識について、今一度見直しをするきっかけとなりました。今後も現状に満足せず、自己研鑽に努めていこうと思います。


